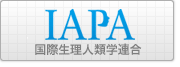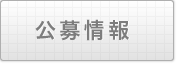設立趣旨
木材は,柱やはりなどの住宅部材として様々な建築物を支えます.また,私たちが直接見たり触れたりする部分にも多用されます.鉄やコンクリートは木材よりも強く,ハードな性能に長けていますが,これらに囲まれて24時間365日生活し続けることは,私たちには恐らく困難です.一方,例えば木の床は,私たちがその上で跳んだり撥ねたりしても壊れない程度の強さを持ちつつ,盛大に転んでも怪我をし難い柔らかさも兼ね備えています.暖色の材面には自然の意匠である木目模様が現れていて,触れると温かさを感じさせます.木材はいわばハードもソフトもこなす材料であり,私たちが生活環境を構築するのに「ちょうどよい」いくつもの性質を有しています.このため,木材は暗黙のうちに「温かい」「自然な」「柔らかい」印象を私たちに与えるようです. このような木材のポジティブなイメージは大いに結構なのですが,人に対する「木の良さ」はどうもイメージ先行になりがちで,科学的な説明が十分ではありません.木材には工芸材料という側面もあるので,あえて「木と人の関係」を科学的に考えることは野暮なのかもしれません.しかし,「木を有効に人の生活に活かして使う」ことを考えると,「木と人の関係」を科学的に考えることがやはり重要に思えてきます. 木材は,鉄やプラスチックスなどの工業材料に比べて物性のばらつきがすごく大きい材料です.そして,私たちはすごく気まぐれな生物です.ばらつく木と気まぐれな人のマッチングを図るには,特別な方法論が必要になると予想されます.木材の物性については,木材科学の分野に多くの物理学的,化学的な研究蓄積があります.一方, “木材屋”が苦手な「人の理解」や「人を測る」部分を補うには,日本生理人類学会の皆様の豊富な研究蓄積を利用させていただく必要があります.単に木をたくさん使えばよい,木ならば何でもよいではなく,どの木をどこにどのように使えば真に人に良いのかを考えることは非常に重要です.木を利用するのは人間です.木と人との関係を科学的に知り,それを活かした利用方法の提案ができることを目指すとともに,関心を持つ方々の情報ハブとなる研究会にできればと考えております.
事務局
部会長:仲村匡司( 京都大学)
E-Mail: nakamasa@@kais.kyoto-u.ac.jp
(@@をひとつにして下さい)

 Top of this page
Top of this page