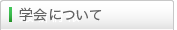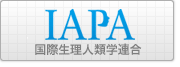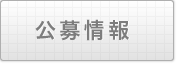日本生理人類学会会長
樋口重和(九州大学大学院芸術工学研究院教授)
このたび2025–2026年度の会長に選出されました。2期目となりますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。1期目は不慣れな中でのスタートでしたが、その経験を糧に、今期はこれまで達成できていない目標を着実に実行したいと考えています。
冒頭は2年前の会長挨拶と重なりますが、本学会の目的は、当該分野の学問の探究と発展を推進し、その成果を広く社会に還元することにあります。また、学会活動は会員の皆様からの会費によって支えられていることから、会員サービスの一層の充実を図ることも重要と考えています。そのために、研究成果を発表しやすく、また会員にとって有益な情報をたくさん発信できる学会でありたいと願っています。この基本的な考えは今も変わっていません。
1期目から新たに開始した取り組みとして、秋のフロンティアミーティング、理事によるリレーウェビナー、学生会員の年会費免除や大会参加費の免除など、さまざまな企画や特典を検討・実施してきました。これらの取り組みは、今期もできるだけ継続したいと考えています。また、来年度は学術大会を年2回開催する予定です。1つは例年どおり5月に熊本県立大学で開催し、もう1つは日本人類学会、日本霊長類学会、日本生理人類学会による3学会連合大会を9月に開催する予定です。連合大会は本学会の歴史において初めての試みであり、通常の生理人類学会にはない発表をたくさん聞けることでしょう。ぜひ、「ヒトとは何か、どこから来て、どこへ向かうのか」などといった人類の根源的なテーマに思いを馳せていただければと思います。
さて、今年1月の生理人類士認定制度ニュースレター(第22号)の巻頭言を執筆する機会をいただき、合格者の皆様に向けて「Out of Africaにかけて」という題でメッセージを送りました(https://jspa.net/certification)。もしよければそちらもご覧ください。編集の方がアフリカをイメージしてラクダの挿絵を添えてくださいました。折角ですのでそのお返しに、ラクダに関する話を読売新聞の編集手帳(2016年1月5日)から紹介します。ある本(※1)からの引用ですが「砂漠にラクダが棲めて、キリンが棲めないのはなぜだろう」という問いから始まっていました。みなさんその答えがお分かりですか?その答えは、「キリンの場合、見渡すかぎりここには砂しかないと悟ってしまいます。幸運にもラクダはそれがわかりません」というものでした。人はラクダに似ている。見えるのは今だけであした何が起きるかは誰も知らないので、希望を抱いて人生の旅を続けることができるとありました。この記事を読んで、研究も同じだと感じました。
最後に、日本生理人類学会も、ある時は人類進化における大きな一歩にならい、ある時は砂漠に棲むラクダの一歩にならい、大きな挑戦と小さな挑戦を続けていきたいと考えています。会員の皆様には、今後とも温かいご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
2025年8月吉日
(※1)特捜部Q-吊るされた女, ユッシ エーズラ オールスン著、早川書房, 2015

 Top of this page
Top of this page